「投資も大事だけど、もしものために生活費の◯ヶ月分は現金で持っておいた方がいい」
そんな言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実際、投資信託やNISAなどでお金を増やしていくことは重要ですが、病気や失業といった予期せぬ出来事が起きたときに頼れるのは、やはり手元の現金です。これが“生活防衛資金”と呼ばれるものです。
生活防衛資金は、収入が一時的に途絶えたときに「最低限の生活を守るための資金」であり、安心して投資や日々の暮らしに向き合うための土台になります。一般的には「生活費の半年〜1年分」が目安といわれていますが、必要額は働き方や家族構成によって変わります。会社員は傷病手当金や雇用保険といった公的制度である程度カバーできますが、自営業やフリーランスにはそれがありません。
わが家では、まず「半年分」を守りのラインと考え、モデルケースで具体的に計算しています。いまはNISAの枠に入れるまで待機させている資金があるため、結果的に2年分ほど現金を持っている状態ですが、基本の考え方は「半年分で十分」というものです。この記事では、わが家の事例をもとに、生活防衛資金の考え方や必要額、制度の違い、実際のメリットまで整理してご紹介します。
1. 生活防衛資金とは?
生活防衛資金とは、収入が止まっても最低限の暮らしを維持できるように備えておく現金のことです。
- 一般的な目安:生活費の半年〜1年分
- 会社員:健康保険の傷病手当金(最長1年6か月・給与の約3分の2)や雇用保険の失業給付があるため、半年分程度でも安心
- 自営業・フリーランス:こうした制度がないため、1〜2年分を現金で備えておくのが理想
2. わが家の生活防衛資金(モデルケースで解説)
わが家では「生活費の半年分=195万円」を目安にしています。
モデルケースとして「夫612万円+妻100万円=年収712万円の家庭」を想定しました。
- 年収:合計712万円
- 手取り:約540万円
年間の支出イメージ
- 基本生活費:30万円 × 12ヶ月 = 360万円
- 特別費(車検・家電など):30万円
- 娯楽費(旅行・外食など):ボーナスから充当(例:50万円)
👉 基本+特別費=390万円(=月約32.5万円)
この金額を基準にすると、
- 半年分=約195万円
- 1年分=約390万円
生活防衛資金の保管は、普通預金に半年分を確保し、夫婦で分散して管理。追加分は、投資口座の「待機資金」として置いています。
3. 公的制度でカバーできる部分
生活防衛資金を「全部自分でまかなう」と思うとハードルが高く感じますが、会社員であれば制度に助けられる部分もあります。
- 健康保険の傷病手当金(最長1年6か月、給与の約3分の2を補填)
- 雇用保険の失業給付(加入年数・年齢で支給日数が変わる)
- 労災保険の補償
特に会社員は「現金半年分+公的制度」で実質1年分以上の安心を得られるケースもあります。
一方で自営業・フリーランスは制度が限定されるため、1〜2年分を現金で備えておくのが安心です。
ケース比較:40歳・月収38万円・勤続20年の場合
生活防衛資金(195万円)を持っている前提で、会社都合と自己都合の違いを見てみます。
| 退職理由 | 失業給付額(60%試算) | 生活防衛資金 | 合計資金 | 生活費換算(月32.5万円) | カバー可能期間 |
| 会社都合退職 | 約205万円 | 195万円 | 約400万円 | 約12.3か月分 | 1年超 |
| 自己都合退職 | 約114万円 | 195万円 | 約309万円 | 約9.5か月分 | 約10か月 |
👉 会社都合なら1年以上の安心が得られますが、自己都合だと10か月程度が限界。
この違いを知っておくだけでも「どのくらい現金を備えておけば安心か」の目安になります。
4. 生活防衛資金があるメリット
生活防衛資金があることで得られるのは、単なる「現金の安心」だけではありません。
- 「何があっても半年は暮らせる」という安心感
- 投資の値動きに振り回されず、長期運用を続けられる
- 余裕のない時期は旅行などを控えると割り切れる
- 普段の生活や学びに前向きになれる
👉 わが家では195万円を生活防衛資金のラインと考え、それ以上は投資など将来のために回しています。
✅ まとめ
- 生活防衛資金は「生活費の半年〜1年分」が目安
- わが家はモデルケースを想定し、390万円を基準に半年分=195万円を目標に設定
- 会社員は制度を組み合わせれば“現金半年分で実質1年分”の安心
- 自営業は1〜2年分を厚めに確保すると安心
- 防衛資金は“安心と自由のバランス”を支える土台
💡 この記事とあわせて読みたい:
▶ 【投資と保険】私がやめた貯蓄型保険と始めた新NISA|比較でわかった違いと実例
▶ わが家のふるさと納税ルール|失敗しない選び方とおすすめ返礼品
▶ 家計簿アプリの選び方と、マネーフォワード活用術



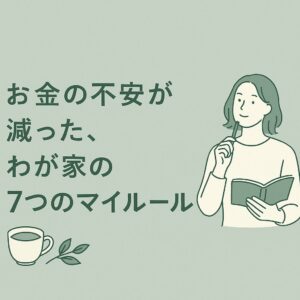


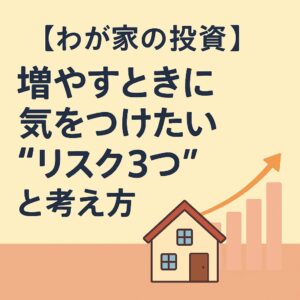



コメント