「保険で備えておけば安心」「貯金が苦手だから、保険で積み立てておこう」——そんなふうに思っていた私が、考え方を大きく変えるきっかけになったのが、ある独立系FPさんとの出会いでした。
これまでわが家は、教育費や老後資金を保険で準備しようと考え、学資保険・外貨建て保険・個人年金などを組み合わせて契約。
保険料の合計は、気づけば年間100万円を超えていました。
「将来のために必要な支出」と思っていたけれど、じわじわと家計を圧迫し、日々の生活にゆとりがなくなっていく感覚がありました。
そんなときに出会ったのが、保険を販売しない中立的なFPさん。
お金の使い方を“制度や仕組み”だけでなく、“気持ちや価値観”から一緒に見直してくれたことで、わが家の「備え方」は大きく変わっていきました。
この記事では、FPさんとの出会いと学び、保険を見直したことで得られた変化をリアルにお伝えします。
保険に安心を詰め込みすぎていた私
これまで私は、「保険で備えること=安心」だと信じてきました。
教育費や老後資金も、保険で準備するのが当たり前のように思っていて、
気づけば家計の中でかなりの金額を保険にまわしていたんです。
でも、保険にお金をかけすぎることで、今の暮らしのゆとりがどんどん削られていたのも事実。
そんなとき出会ったのが、保険を売らない独立系FPさんでした。
出会ったのは、保険を売らないFPさん
加入から1年ほどたち、「このままでいいのかな?」とモヤモヤしていた頃。
以前からブログを読んでいた方が独立してFPを始めたというお知らせを見かけ、
「この人に相談してみたい」と思ったのがきっかけです。
驚いたのは、「保険を売る立場ではない」ということ。
相談料はかかるけれど、保険会社に属さない中立な立場で、私たちの家計を一緒に考えてくれる存在に安心感を覚えました。
FP=保険屋さん、と思っていた過去
それまで「FPです」と名乗る人に相談すると、保険のパンフレットが出てきて、
見積もりや提案をされるのが当たり前だと思っていました。
実際、保険の営業の方がFP資格を持っていることも多く、
「FP=中立な立場」とは限らないのが現実です。
だからこそ、本当の意味で「自分に必要な保障や備え」を相談できる場所が、私にはありませんでした。
教えてもらったこと、変わった考え方
FPさんには、iDeCoやつみたてNISAの基本から丁寧に教えてもらい、
ライフプラン表も一緒に作ってもらいました(相談料:数万円)。
当時の私は、「教育費は保険でコツコツ貯めるもの」と思い込んでいましたが、
「今の家計で教育費はまかなえるのでは?」と言われたことが、とても衝撃的でした。
“今あるお金でできること”を考える視点が、自分にはなかったことに気づかされたんです。
それからは、「貯める」「備える」の意味が、少しずつ変わっていきました。
保険と貯蓄(資産形成)を分ける
もうひとつ大きな気づきは、保険は保障、資産形成は別で考えるということ。
私はそれまで、「保険の中に安心も、将来のお金も詰め込めばOK」と思っていたんだと思います。
でも、保障が必要な時期や目的は限られていて、
貯める・育てるお金は、もっと自由でよくて、自分でコントロールしていけると知りました。
相談後、わが家がしたこと
- 入っていた保険を1つずつ見直し、不要なものは解約
- 必要な保障は、掛け捨て型に切り替え
- 残ったお金で、つみたてNISAやiDeCoをスタート(※当時は旧制度)
FPさんが「これに入りましょう」と押しつけるのではなく、
私たち家族の価値観を聞いたうえで、選択肢を一緒に考えてくれたことが大きかったです。
解約でマイナスになったけれど…
一括払いしていた保険などを解約したことで、返戻金は払った金額を下回り、
トータルで約150万円のマイナスになりました。
最初はショックもありましたが、
「このまま払い続けてさらに自由がなくなるより、今ここで見直すべき」と判断。
手元に戻ってきた資金の一部は、つみたてNISAやiDeCoにまわし、
将来の教育費や老後資金に向けて、自分たちで“育てていく”ことにしました。
自分で仕組みを理解して納得してお金を動かすことで、
「備える力」が育っている実感があります。
今振り返って思うこと
FPさんに相談していなければ、きっと今も高額な保険料を払い続けていたと思います。
「安心のために入っていたはずの保険」が、逆に不安のもとになっていた——
そんな家計から抜け出せたのは、中立な立場で寄り添ってくれる存在に出会えたからでした。
お金の知識や制度は、検索すればある程度わかります。
でも、「それをどう活かすか」を一緒に考えてくれる人の存在は、本当に大きいと感じています。
💡 この記事とあわせて読みたい:

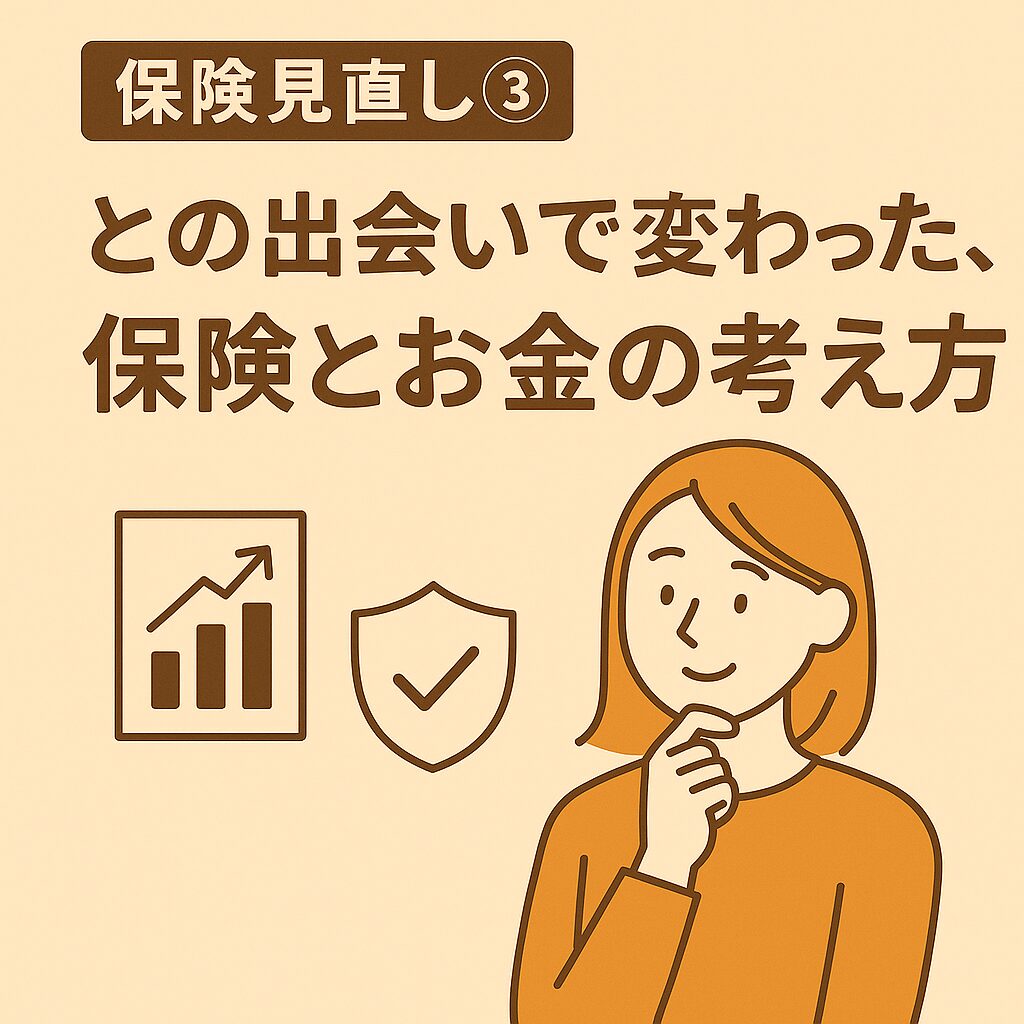

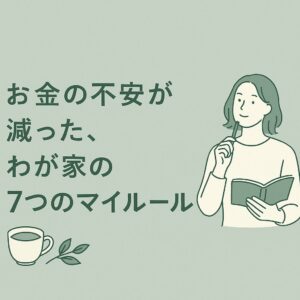


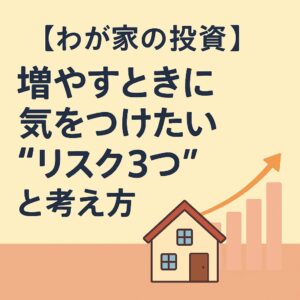



コメント